旅行や勉強?に行った先で、古い燈籠や水鉢、石像などを集めて
みました。でも、ただ古けりゃ良いってもんでもありません。
やっぱり、姿、形が良く、品のある物がイイですね。
高さは目測、石質は推察です。アシカラズ。
韓国 慶尚北道の石造品です。
日本には、平安時代以前の燈籠が不完全のがいくつかしか
残っていません。仏教と共に渡来して来た石燈籠のルーツに
興味を覚えました。
参考までに
三国時代 ( 〜飛鳥時代終わり)
統一新羅時代(飛鳥時代終わり〜平安時代初め)約350年間
高麗時代 (平安時代初め〜室町時代中ごろ)約450年間
李朝時代 (室町時代中ごろ〜明治初め) 約500年間
|
|
| 石燈籠の各部名称 |
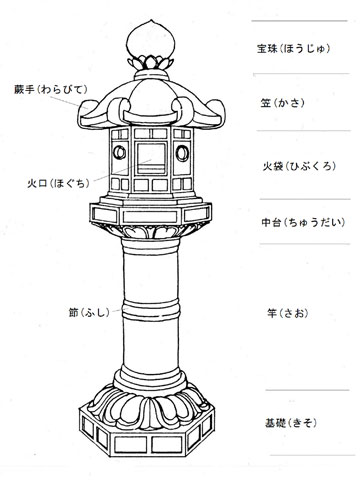 |
|
| 奉化郡 |
 |
|
鷲棲寺石燈
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高7尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
鷲棲寺 普光殿前 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |
| 備考 |
竿、修復痕あり
現地案内板には、高麗時代初めの造成とあるが
あまり差はないが、三層石塔と同じ頃
統一新羅時代末867年頃の造成ではないか?
大きな火袋と笠の様な宝珠が特徴
|
|
|
 |
|
鷲棲寺石造毘盧遮那佛坐像
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高4尺 |
形状 |
|
| 所在 |
鷲棲寺 普光殿内 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |
| 備考 |
光背は、木造
三層石塔と同じ頃、統一新羅時代867年頃の造成か?
ただ、他の場所から持ち込まれたという説もあり
|
|
|
 |
|
鷲棲寺石造毘盧遮那佛坐像台座
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高3尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
鷲棲寺 普光殿内 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |
| 備考 |
中台8面に坐像
|
|
|
 |
|
鷲棲寺三層石塔
|
| 時代 |
統一新羅時代 867年 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高12尺 |
形状 |
|
| 所在 |
鷲棲寺 寂黙堂横 慶尚北道 奉化郡 物野面 皆丹里1 |
| 備考 |
2、3層塔身、相輪後補
石塔の中から高さ9.5cmの舎利石盒(国立中央博物館蔵)が出土し
年代わかる
この三層石塔は、鷲棲寺の中でも高いところにあり
ここからの眺めがいい
|
|
|
| 栄州市 |
 |
|
浮石寺無量寿殿前石燈
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高10尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
浮石寺 無量寿殿前 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |
| 備考 |
完存、さすがに国宝素晴らしい
火袋4面火口、4面菩薩像 |
|
|
 |
|
浮石寺三層石塔前石燈部材
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高5.5尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
浮石寺 三層石塔前 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |
| 備考 |
基礎、竿、笠のみ
完存だと8尺燈籠に
国宝の無量寿殿前石燈より小ぶりでシンプル |
|
|
 |
|
浮石寺醉玄庵石燈部材
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高3尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
浮石寺 梵鐘閣すぎて左側 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |
| 備考 |
三層石塔前石燈の火袋とは別物なのか? |
|
|
 |
|
浮石寺幢竿支柱
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高14尺 |
形状 |
|
| 所在 |
浮石寺 天王門前 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |
| 備考 |
蓮華文様を刻んだ竿受けの台座あり |
|
|
 |
|
浮石寺石造釈迦如来坐像
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高7尺 |
形状 |
|
| 所在 |
浮石寺 慈忍堂内中央 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |
| 備考 |
浮石寺の東の寺址から移す
光背はないが、台座の獅子などの彫刻が素晴らしい |
|
|
 |
|
北枝里石造釈迦如来坐像 西仏
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
像高3.4尺 台座高3.4尺 |
形状 |
|
| 所在 |
浮石寺 慈忍堂内左側 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |
| 備考 |
浮石寺の東側の山を越えた廃寺址にあったものを移す
台座8角 |
|
|
 |
|
北枝里石造釈迦如来坐像 東仏
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
像高3.3尺 台座高3.5尺 |
形状 |
|
| 所在 |
浮石寺 慈忍堂内右側 慶尚北道 栄州市 浮石面 北枝里148 |
| 備考 |
浮石寺の東側の山を越えた廃寺址にあったものを移す
西仏、東仏とも、同じ作り手 |
|
|
 |
|
宿水寺址幢竿支柱
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高13尺
|
形状 |
|
| 所在 |
紹修書院 入口右脇 慶尚北道 栄州市 順興面 内竹里158 |
| 備考 |
朝鮮時代の儒教の学校、紹修書院の入口に建っている
この敷地に統一新羅時代、宿水寺があった
慶州市内三郎寺址幢竿支柱に似ている |
|
|
 |
|
宿水寺址石燈部材
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高5.5尺
|
形状 |
8角 |
| 所在 |
紹修書院 蔵書閣前 慶尚北道 栄州市 順興面 内竹里152-8 |
| 備考 |
8角石燈の基礎、竿、笠
紹修書院の敷地内に
|
|
|
 |
|
毘盧寺石燈部材
|
| 時代 |
高麗時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高3.5尺
|
形状 |
8角 |
| 所在 |
毘盧寺 梵鐘閣脇 慶尚北道 栄州市 豊基邑 三街里390 |
| 備考 |
8角石燈の基礎、竿、笠
|
|
|
 |
|
栄州三街洞幢竿支柱
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高14尺
|
形状 |
|
| 所在 |
毘盧寺 一柱門脇 慶尚北道 栄州市 豊基邑 三街里661-29 |
| 備考 |
支柱下部は荒く削っている
名称が毘盧寺幢竿支柱では、ダメなのだろうか? |
|
|
 |
|
毘盧寺石塔
|
| 時代 |
統一新羅、高麗時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高10尺 |
形状 |
|
| 所在 |
毘盧寺 寂光殿前 慶尚北道 栄州市 豊基邑 三街里390 |
| 備考 |
8角石燈の笠、石塔の笠や台座など、複数の種類の部材で
くみあげている
ピカピカの新しい石塔よりこのお寺に合っている
|
|
|
| 慶山市 |
 |
|
仏窟寺石燈
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高8尺
|
形状 |
8角 |
| 所在 |
仏窟寺前庭 慶尚北道 慶山市 瓦村面 江鶴里5 |
| 備考 |
三層石塔の前に建っている
装飾のない火袋が破損しているが完存 |
|
|
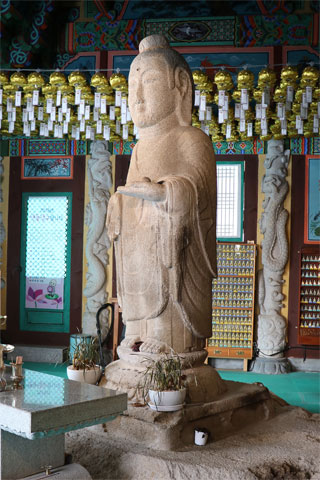 |
|
仏窟寺石造立佛像
|
| 時代 |
高麗時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高8尺
|
形状 |
|
| 所在 |
仏窟寺薬師寶殿内 慶尚北道 慶山市 瓦村面 江鶴里5 |
| 備考 |
地上にある花崗岩の一枚岩の上に台座を彫刻し
その上に仏像を建てている |
|
|
 |
|
嶺南大学石燈中台
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
幅3尺
|
形状 |
8角 |
| 所在 |
嶺南大学博物館前庭 慶尚北道 慶山市 造永洞321 |
| 備考 |
8角石燈の中台 |
|
|
 |
|
嶺南大学石燈基礎
|
| 時代 |
高麗時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
幅2.5尺
|
形状 |
|
| 所在 |
嶺南大学博物館前庭 慶尚北道 慶山市 造永洞321 |
| 備考 |
8角石燈の基礎
ホゾ穴径4寸 |
|
|
| 清道郡 |
 |
|
雲門寺金堂前石燈
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高8.6尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
雲門寺 金堂前 慶尚北道 清道郡 雲門面 新院里 1789 |
| 備考 |
特徴は、中台と基礎の蓮弁の中の柏の葉の様な装飾
雲門寺石燈詳しくは
|
|
|
 |
|
雲門寺毘盧殿前石燈
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高9尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
雲門寺 毘盧殿前 慶尚北道 清道郡 雲門面 新院里 1789 |
| 備考 |
金堂前石燈と様式、規模同じ |
|
|
| 漆谷郡 |
 |
|
松林寺石燈
|
| 時代 |
高麗時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高8尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
松林寺 大雄殿前 慶尚北道 漆谷郡 東明面 九徳里91-6 |
| 備考 |
竿後補、寄せ集めか?
松林寺石燈詳しくは
|
|
|
 |
|
松林寺石燈基礎
|
| 時代 |
高麗時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
幅3尺 |
形状 |
8角 |
| 所在 |
松林寺 大雄殿前 慶尚北道 漆谷郡 東明面 九徳里91-6 |
| 備考 |
8角石燈の基礎 |
|
|
 |
|
松林寺幢竿支柱
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高9尺 |
形状 |
|
| 所在 |
松林寺 寺外 慶尚北道 漆谷郡 東明面 九徳里91-6 |
| 備考 |
1柱、片側だけ
寺の外、畑の中に |
|
|
| 星州郡 |
 |
|
法水寺址幢竿支柱
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高12尺
|
形状 |
|
| 所在 |
慶尚北道 星州郡 修倫面 |
| 備考 |
海印寺近くの畑の中に
|
|
|
| 高霊郡 |
 |
|
池山里幢竿支柱
|
| 時代 |
統一新羅時代 |
石質 |
花崗岩 |
| 寸法 |
高10尺 |
形状 |
|
| 所在 |
慶尚北道 高霊郡 大伽耶邑 池山里3-5 |
| 備考 |
街中にポツンと二本の柱だけが残っている
とてもきれいな彫刻、全体に整っている |
|
|
|
|
| HOME|韓国北部|全羅北道|全羅南道|慶尚北道|慶尚南道 釜山 |
| 大邱|慶州中心|慶州郊外|慶州博物館 |
| 京都北|京都市|京都南|奈良市|奈良市外|大阪府|近畿 中部 |
| 滋賀県北部|東近江市|蒲生郡|滋賀県南部|中国 四国 九州|関東 東北 |
|
|
|

